|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 図書館のめざすもの | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| えるる五色・・・名前の由来 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
住民より公募しました。 小さな子どもから高齢者まで、末永く( L ong)愛され( L ove)、様々な情報や知識を 得る ことができるよ うに、との願いが込められています。 頭文字の "L""得る" の組み合わせと、語感の良さからえるる五色の愛称が選ばれました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| シンボルマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
|
住民より公募しました。
本を読んでいるうさぎの周りに梅の花びらをあしらっています。梅の花は、 学問の神様として崇められる菅原道真公(鮎原河上神社天満宮に祭られて いる)が、愛した花です。 『東風吹かば においおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春なわすれそ』 菅原公御神詠の歌 |
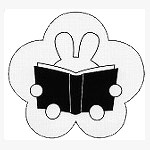
|
||||||||||||||||||||||||||||